2019/10/09
社会学・社会福祉・心理学等の書籍の買取


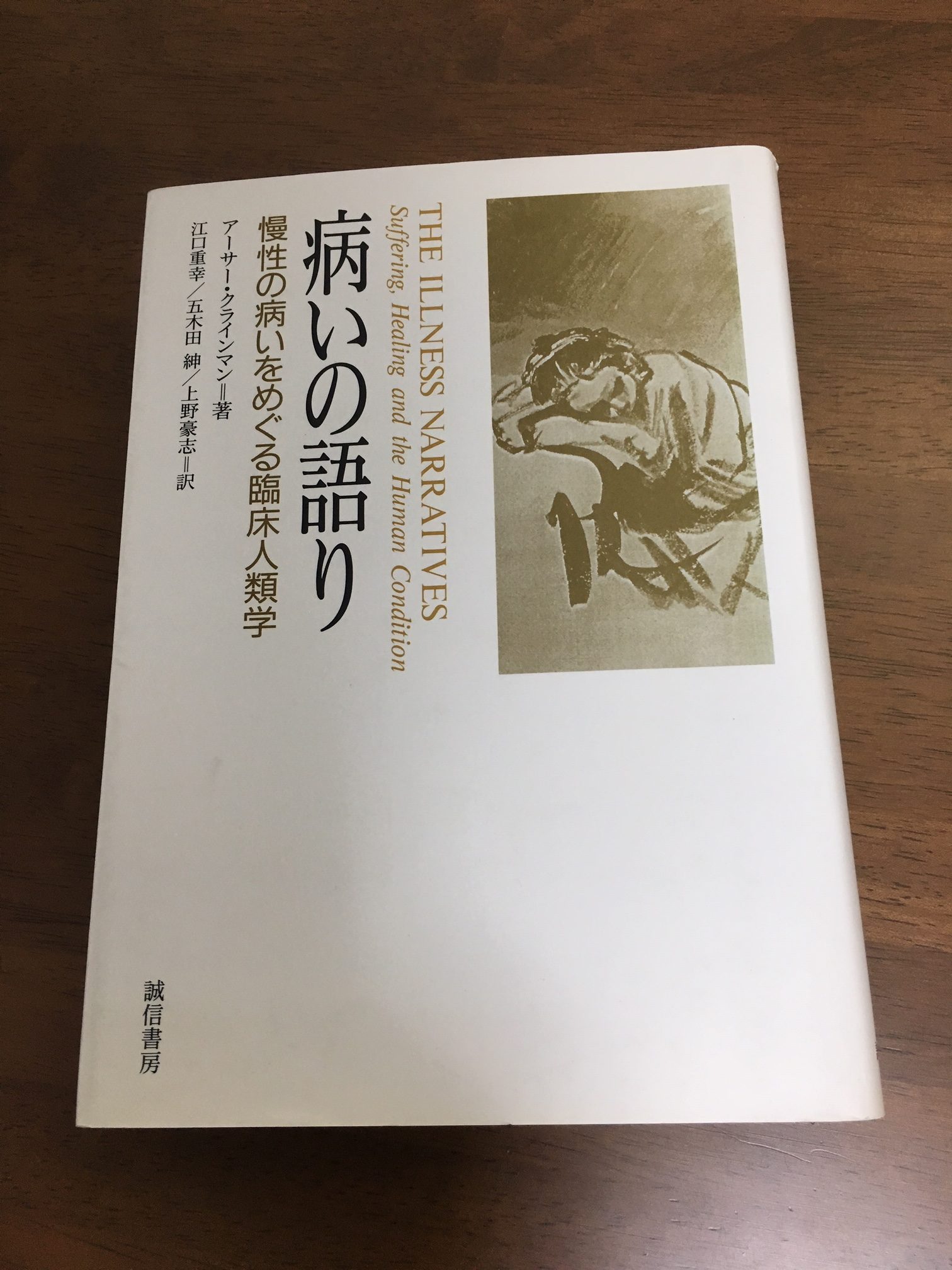
今回は社会学や社会福祉、それに関連する心理学や医療倫理などの書籍を多数買取させていただきました。以下に良い査定額をお付けできた本をご紹介します。
「アイデンティティ・ゲーム―存在証明の社会学」
「精神医療ユーザーのめざすもの―欧米のセルフヘルプ活動」
「臨床人類学―文化のなかの病者と治療者」
「慢性疾患を生きる―ケアとクオリティ・ライフの接点」
「セルフヘルプ・グループ」
「高齢者エンパワーメントの基礎―ソーシャルワーク実践の発展を目指して」
「セルフヘルプ・グループの理論と展開―わが国の実践をふまえて」
「病いの語り―慢性の病いをめぐる臨床人類学」
「公人社 知る権利とプライヴァシー 21世紀のアクセス権への前進 下河原忠夫著 1992年」
「自立生活運動と障害文化―当事者からの福祉論」
「精神障害者の地域生活支援―統合的生活モデルとコミュニティソーシャルワーク」
「べてるの家の「非」援助論―そのままでいいと思えるための25章 (シリーズ ケアをひらく)」
「セルフヘルプグループ―わかちあい・ひとりだち・ときはなち」
「すべてのサービスは患者のために―伝説の医療機関“メイヨー・クリニック”に学ぶサービスの核心 (マグロウヒル・ビジネス・プロフェッショナル・シリーズ)」
「医療の政策過程と受益者―難病対策にみる患者組織の政策参加」
「スティグマの社会学―烙印を押されたアイデンティティ」
「脱病院化社会―医療の限界 (晶文社クラシックス)」
などなど。
リスト一番上の「アイデンティティ・ゲーム―存在証明の社会学」は、以前こちらのブログの別記事にて紹介させていただきましたが、面白かったです。
さて、今回タイトルから気になりました本は「病いの語り―慢性の病いをめぐる臨床人類学」です。「慢性の病い」と「臨床人類学」という取り合わせ、浅学なわたくしは初めてお目にかかりました。
著者はハーヴァード大学医学部教授のアーサー・クラインマン。邦訳版である本書は1996年4月に第一刷が発行されています。このクラインマン氏は1970年代から始まる医療人類学と呼ばれる領域の草分け的存在なのだそうです。医療人類学という言葉を一言で定義するのは難しそうですが、こちらの本を読む限りでは、病気というのは各社会や文化によってその持つ意味合いが随分違うことから、医療・治療における文化人類学的な側面の解釈をすることで臨床に役立てようとする学問領域なのかなと理解しました。また、著者はまず、本作中で「病い(illness)=患者目線」、「疾患(disease)=治療者目線」、そして、「病気(sickness)=社会目線」を定義しなおすことで、治療者目線の「疾患」ではなく、患者が経験するところの「病い」の「語り」を重視すべきという立場を明確にしています。これがタイトルの意味するところなのですね。
本書中、特に「症状と障害の意味」や「病いの個人的意味と社会的意味」といった導入部2章は、どちらかというと哲学的な概念も入り混じって、平たく言えば分かりやすいものが少し分かりにくく書かれている気がしましたが、第3章以降からは本書の中心的な部分となる具体的な「病いについて語られたストーリー」となっており、慢性的な病いを得た人が語ること、そして、それを傾聴することについての重要性が分かってきます。
なにも人類学的な視点などを取り入れなくても、患者の訴えを傾聴することは治療者には当たり前に期待されていることのように思えますが、曖昧ではっきりしない「やさしさ」や「気配り」のような個人の資質によるところが大きいものではなく、こうして体系立てた知識として臨床者が身につけることができれば、それだけでも十分意味のあることなのだろうな、と感じました。
こちらを読みながら、以前ニュースになった、東京都F市の病院での人工透析治療を挫折してしまった患者と、治療を断念してしまった医師をめぐる出来事を思い出していました。日本では慢性の病いを得てしまった人への社会(時には治療者ですら)的意味づけがシビアなのでしょう。この件では、病いを得てしまった人の生産性がどうだとか、治療そのものの意味だとか、一般に流布する解釈が彼女を追い詰めてしまった一面もあると思います。本書は20年以上の前の作ですが、未だ臨床者や慢性的な病いを生きる当事者(患者、その家族)と治療者に考えなおすべき視点があることを提示しているのではないでしょうか。
今回も良書をたくさんお譲りいただき、ありがとうございました!


